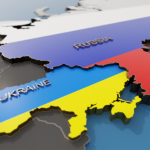習近平氏の素顔から、習近平政権はどこへ向かうのかを読む
習近平氏の、中国共産党内の素顔を知ろう
日本では、中国共産党の歴史や構造を正確に記した書籍が少なく、報道も自由主義陣営に属する社会の立場から行われています。
中国共産党のトップとしてタブーであった第三期目という長期にわたって政権を維持する習近平氏を理解し、中国の政治が、今後どこに向かうのかを予測して、ビジネスのベクトルを決めなければならない私たちにとって、習近平氏を動かすものを知るためには、習近平氏が、どのようなヒトであるのかを、しっかりと把握しなければなりません。…
続きを読む
日本では、中国共産党の歴史や構造を正確に記した書籍が少なく、報道も自由主義陣営に属する社会の立場から行われています。
中国共産党のトップとしてタブーであった第三期目という長期にわたって政権を維持する習近平氏を理解し、中国の政治が、今後どこに向かうのかを予測して、ビジネスのベクトルを決めなければならない私たちにとって、習近平氏を動かすものを知るためには、習近平氏が、どのようなヒトであるのかを、しっかりと把握しなければなりません。…
続きを読む